10/27(金)にドイツ・DAAD (Der Deutsche Akademische Austrauschdienst)と日本学術振興会(JSPS)の交流事業として、ワークショップ「Waseda-Kassel Environmental Economics Workshop」が開催されました。本ワークショップでは、ドイツ・カッセル大学、早稲田大学の研究者に加え、東京工業大学、福井県立大学、政策研究大学院大学、成城大学の研究者も参加しました。

ワークショップでは、家庭の環境意識とグリーン行動に焦点が当てられました。家庭部門の電力消費は、世界全体の約4分の1を占めることが知られています。そのため、家庭のエネルギー消費の原動力となるものや、省エネや持続可能な商品への需要を高める潜在的な方法を理解することは、世界のエネルギー需要を削減する上で極めて重要となります。
Andreas Ziegler教授(ドイツ・カッセル大学)は、「The expressive effect of legal norms」と題し、持続可能な商品に対するドイツの家計の選好と、公正な労働条件を保証する新しい法律に対する反応を検証しました。検証では、持続可能な靴下に関する選択実験を行い、そのような製品に対する支払い意思額(WTP)を推定しました。その結果、興味深いことに、回答者は法律導入の影響を受けないことが示されました。
Gunnar Gutsche教授(ドイツ・カッセル大学)は、中井美和教授(福井県立大学)との共同研究として「Cultural values and sustainable investment behavior in Japan」と題し、議論しました。発表では、日本でESG投資が遅れていることを指摘した上で、その原因が日本と欧米との文化の違いによるものではないかと結論付けました。そして、今後は「和」「生きがい」「もったいない」といった考え方による潜在的な影響を検討し、日本人が持つ持続可能性に対する考え方をESGの定義に含められないかを研究するとしています。
Aline Mortha氏(早稲田大学)は、OECDの最新の調査結果を紹介しながら、気候変動に対する意識とグリーン行動の心理的決定要因について議論しました。環境意識は重要である一方、気候変動への取り組みに個人的な意欲を感じている回答者や気候変動による影響を受けやすいと考えている回答者ほど、グリーン家電の購入や省エネ行動に取り組む傾向が強いと結論付けました。
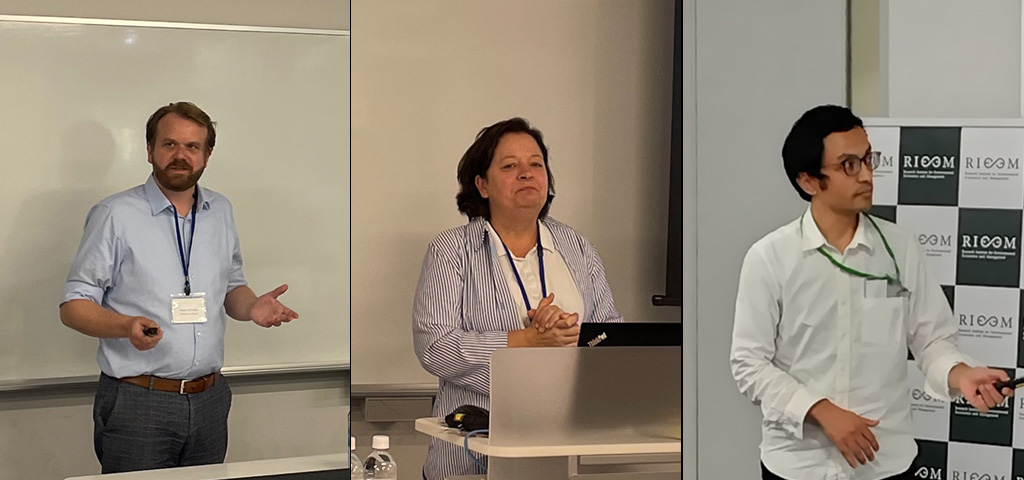
休憩後、Heike Wetzel教授(ドイツ・カッセル大学)が登壇し、ドイツで実施された選択実験の最新結果について議論しました。同教授は、太陽光発電(蓄電池付きも含む)の購入を検討している世帯を対象に、太陽光発電システムのレンタルと購入の希望を評価しました。その結果、回答者は蓄電池付きの太陽光発電システムをレンタルするよりも購入することを好むことが分かりました。また、地域エネルギー共有システムに対する支払意思額(Willingness To Pay: WTP)が正であることも分かりました。
Ngawang Dendup助教(早稲田大学)は、ブータンにおける段階制の電力価格に関する構造推計の結果を議論しました。発表では、電力消費者が必ずしも電力料金の追加的な上昇に反応しているわけではなく、電力料金の平均額に反応する人もいれば、単に段階的な価格設定に困惑している人もいることが示されました。
最後に、参加者で記念撮影を行いました。本ワークショップは多数の研究者が参加し、盛況のうちに終了しました。
