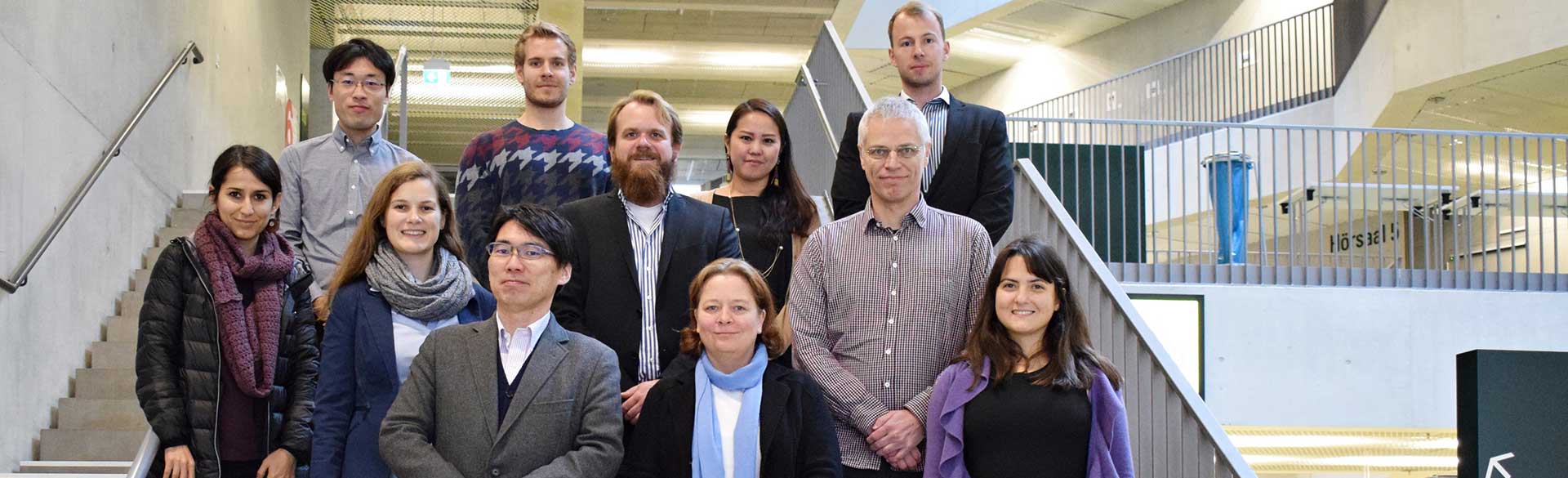日中韓で共同しながら気候変動政策を促進するための研究を実施しています。2016年より、日中韓のカーボンプライシングに関するフォーラムに参加してきました。 このフォーラムを契機に、中国・清華大学と韓国・慶熙大学校との相互交流並びに協同研究を実施して、日中韓の排出量取引制度について意見交換を行っています。 2017年には清華大学・能源環境経済研究所チームの早稲田訪問を受け、 同年秋には、同大学の周剣准教授を招聘し、「パリ協定とカーボンプライシング」と題した国民対話シンポジウムを開催しました。 2018年には環境経済・経営研究所のメンバーが清華大学を訪問し、ワークショップで研究報告をしました。
2019年には、韓国・慶熙大学校を訪問しワークショップを行い、さらに同大学のHyungna Oh教授を招聘し、国民対話シンポジウム「カーボンプライシングの制度オプションの検討」開催しました。
これらの交流を踏まえ、清華大学・MaoshengDuan教授、慶熙大学校Hyungna Oh教授と連携し、2019年8月に東アジア環境・資源経済学会(北京)で、企画セッション「Carbon Pricing in East Asia」を主催しました。 現在、その成果はEnvironmental Economics and Policy Studiesの特集号Carbon Pricing in East Asiaとして組まれ、東京都排出量取引制度の効果に関する研究の成果等が発表されています。
アジアの農村の家庭では、調理の際に薪炭材等の固形燃料を利用することにより、室内空気汚染の問題を引き起こすことが知られています。 調理に従事する女性や子供が健康被害を受ける深刻な問題です。 この問題解決のために、ブータン並びにインドの室内空気汚染問題について、現地調査やミクロデータを活用した研究を行ってきました。 ブータンについては、室内空気汚染の健康に関する情報の重要性を明らかにした研究をEnergy Policyに公刊しました。 インドについても、主観的確率に注目した研究などを実施しています。 今後もこの問題の研究を続けていく予定です。
アジア各国は経済成長とともに、エネルギー消費が増大し、温室効果ガスの排出にもつながっています。そこで、アジア各国での省エネルギーの重要性が増しています。 そこで、弊研究所では、フィリピンのアテネオ・デ・マニラ大学のMajah Ravago准教授 と連携して、二つのプロジェクトを実施しています。
近年、先進国では、行動経済学のNudgeを用いて省エネ行動を促進する方法が成功しています。 本研究プロジェクトは、フィリピンの農村をとりあげ、と電力会社の協力を得て、社会実験を行いました。 発展途上国でもNudgeを用いた節電実験が成功するかを検証しています。 Ravago准教授、ハワイ大学の樽井礼教授、Brucal博士と連携して実施しています。
家計部門ではエアコン利用による電力消費量が多く、フィリピン国内のエアコン保有者も年々増加しています。 そこで家計部門が取り得る有効な省エネ行動として、省エネエアコンの買い替え・利用に着目し、消費者に調査を実施することで、エアコンの購入決定に与える要因、および、省エネエアコン購入を促進する情報の特定化を行っています。 本研究は早稲田大学理工学術院の齋藤潔教授と連携し、分野横断型のアプローチを採用しながら研究を進めています。